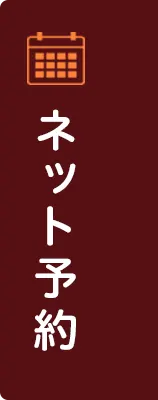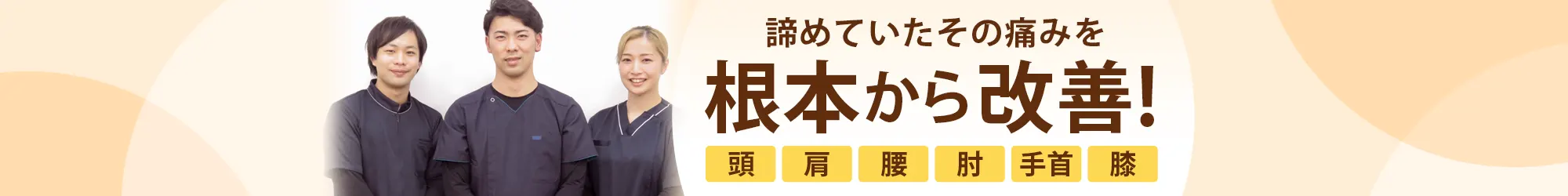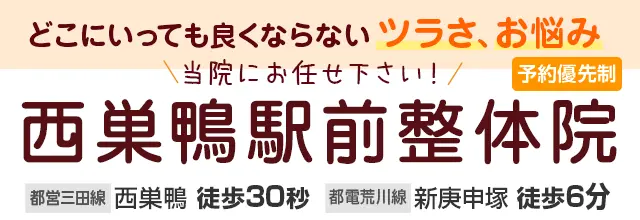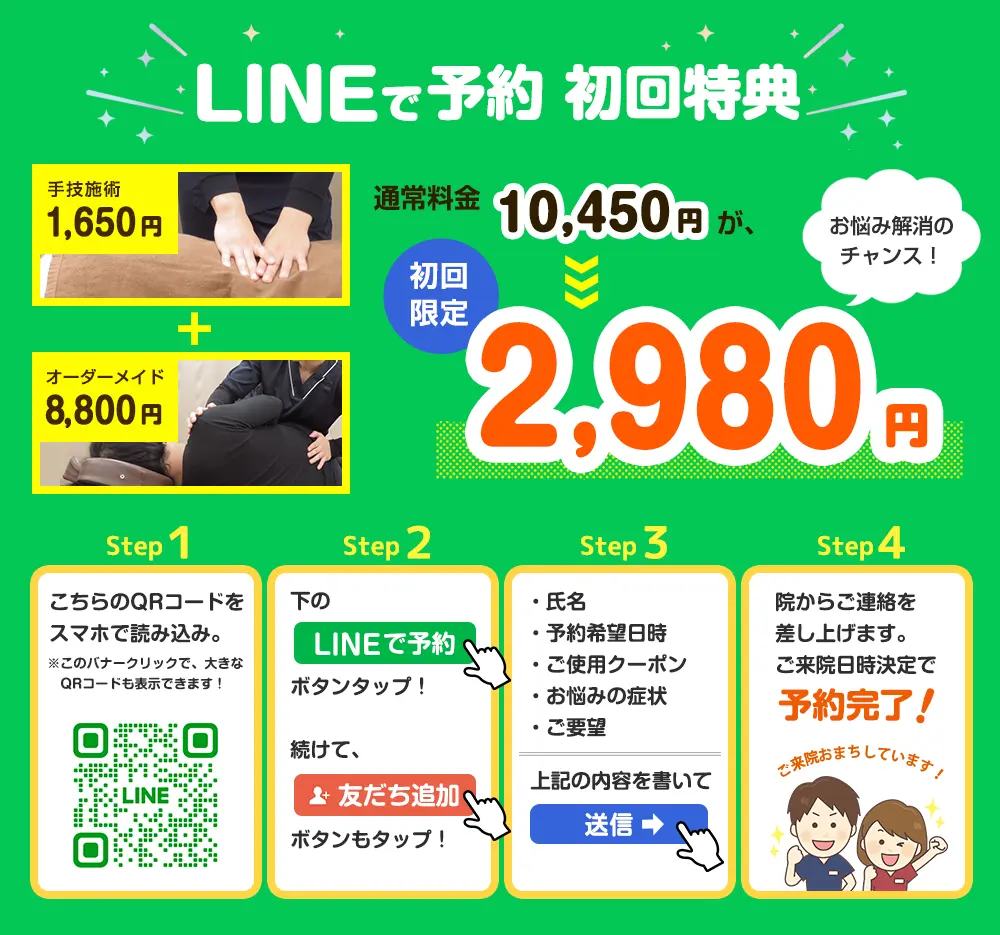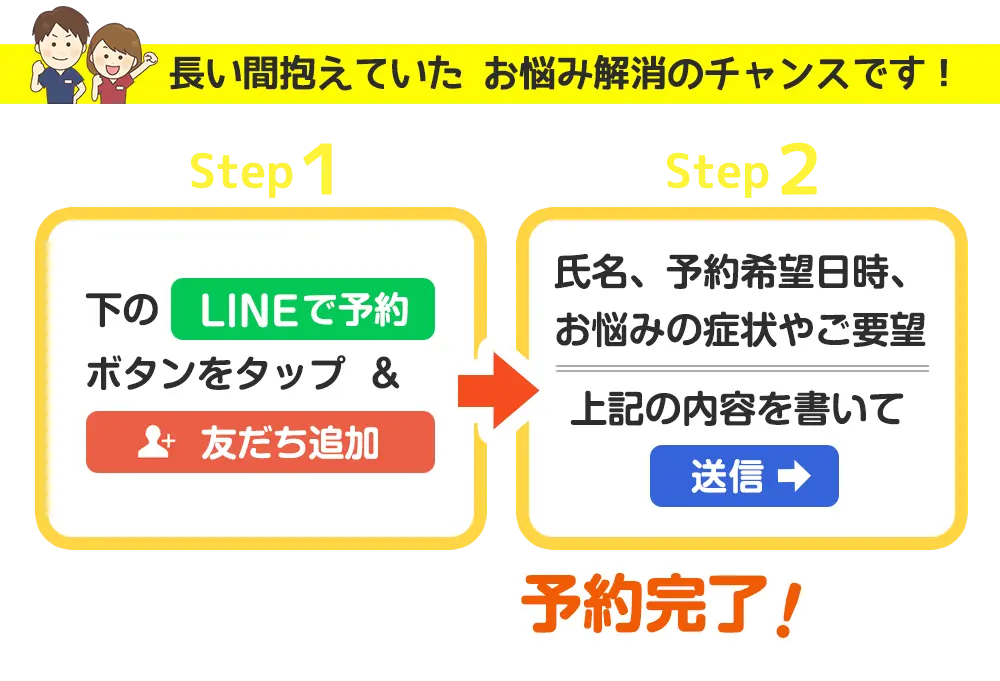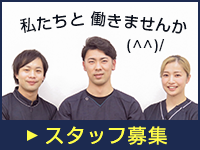Q.半月板とはなんですか?
A.1. 半月板の位置と形
半月板(はんげつばん)は、膝関節の中にあるC字型の軟骨組織です。
膝には左右に内側半月板と外側半月板の2つがあります。
大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)の間に挟まって存在しています。
2. 半月板の役割
衝撃吸収:ジャンプや走行時の衝撃を和らげるクッションの役割。
関節の安定化:大腿骨と脛骨の骨の噛み合わせを安定させる。
潤滑作用:関節液を均等に広げ、関節の動きを滑らかにする。
荷重分散:体重が一部に集中しないように分散させ、関節の摩耗を防ぐ。
3. 半月板の構造
外側:血流があり、損傷しても自然治癒や縫合で回復しやすい部分。
内側:血流が乏しく、自然治癒はほぼ期待できず、損傷すると手術が必要になることが多い。
4. 半月板の損傷リスク
スポーツ外傷型:サッカー、バスケットボール、柔道などで膝をひねる動きによって起こる。
変性損傷型:中高年で徐々に摩耗して切れるタイプ。特に大きな外傷がなくても発生する。
5. 半月板の健康を保つには?
大腿四頭筋やハムストリングスを鍛えることで膝関節を安定させる。
柔軟性を高めて膝への負担を減らす。
体重コントロールで関節の過剰な負担を避ける。
西巣鴨、庚申塚、北区西ケ原地域にお住まいの方はもちろん、その他の地域の方も大歓迎です!
Q.半月板損傷の原因はなんですか?
A.半月板損傷は年齢や発生機序によって症状や特徴が異なります。
1. 外傷性半月板損傷(若年者・スポーツ選手に多い)
スポーツでの急な動き。サッカー、バスケットボール、ラグビーなどで膝をひねる動作で損傷しやすくなります。
ジャンプ着地時の衝撃、急停止・急旋回の動き、交通事故や転倒。
強い外力が膝にかかることで半月板が裂ける。
靭帯損傷に合併することもあります。
特に「前十字靭帯」断裂と一緒に損傷するケースが多い。
急な痛み・腫れ・膝がロックする(動かなくなる)などの症状が出やすい。
2. 変性型半月板損傷(中高年に多い)
加齢による摩耗:半月板は年齢とともに弾力が失われ、硬くなり、裂けやすくなる。
日常生活の負担:階段昇降、正座、しゃがみ動作の繰り返し。
明らかな外傷がなくても発生することがあります。
例として「椅子から立ち上がったときに突然膝が痛くなった」というケースも。
特徴:はっきりしたケガの記憶がなく、膝の痛みや腫れ、違和感が徐々に出る。
3. リスク要因
肥満:膝にかかる荷重が増加し、半月板への負担が大きくなる。
筋力不足:大腿四頭筋やハムストリングスの弱さが膝の不安定性を招く。
過去の膝のケガ:靭帯損傷や骨折の既往があると再発リスクが高い。
遺伝的要因:膝の形状(O脚・X脚)が影響することもある
膝の痛みがある方は是非一度と当院にご連絡下さい。
Q.半月板損傷にあける施術方法はありますか?
A.半月板損傷の治療法は、損傷の部位・大きさ・年齢・活動レベル・症状 によって異なります。保存療法と手術療法の2つに分けられます。
1. 保存療法(手術をしない方法)
軽度の損傷や変性型で、膝の動きに大きな制限がない場合に選択されます。
安静・生活指導
痛みが強いときは膝を休ませ、無理な動きを避ける。
階段や正座などの負担を減らす。
また、骨格の歪みからも姿勢不良やバランスが悪くなり、膝への負担がかかりやすくなってしまいますので、骨格矯正や姿勢矯正もおすすめです。
【薬物療法】
消炎鎮痛薬(NSAIDs)で炎症や痛みを和らげる。
ヒアルロン酸注射で関節内の潤滑を改善。
【理学療法(リハビリ)】
大腿四頭筋やハムストリングスの筋力強化。
関節可動域訓練。
バランストレーニングで膝の安定性を高める。
【装具療法】
膝サポーターで関節の安定を補助。
2. 手術療法(関節鏡手術が主流)
保存療法で改善しない場合や、ロッキング(膝が動かなくなる)がある場合に検討されます。
部分切除術(部分切除関節鏡手術)
損傷した半月板の不安定な部分だけを切除し、形を整える。
回復が早く、数週間でスポーツ復帰できることもある。
ただし切除が多いと将来的に変形性膝関節症のリスクが高まる。
【縫合術(半月板修復術)】
損傷した部分を糸で縫い合わせ、自然治癒を促す。
若年者や血流のある「赤帯領域」の損傷に適応。
回復に時間がかかり、術後の安静やリハビリが長期になる。
【半月板移植術】
損傷でほとんど機能を失った場合、ドナーや人工半月板を移植。
日本ではまだ症例数が少なく、特定の施設で行われている。
上記のように手術の段階まで症状が進行してしまうと長期に渡りリハビリが必要になったりや痛みが続いてしまいます。
そうなる前に当院で検査や施術をすることがおすすめです
Q.施術後のリハビリにはどれくらいかかりますか?
A. 術後・施術後のリハビリ
【急性期(術後1〜2週)】
・腫れ・炎症の管理(アイシング、圧迫)。
・軽い可動域訓練。
【回復期(術後2〜6週)】
・筋力トレーニング(特に大腿四頭筋)。
・体重負荷を徐々に増やす。
【復帰期(術後2〜6か月)】
・ジョギング → ダッシュ → スポーツ動作へと段階的に復帰。
リハビリの期間としまして数週間~数か月かかる場合がありますが、なるべく早い段階で施術からリハビリを開始することでお身体のご負担も最小限に
抑えながら改善に向かうことが可能となります。
痛みがなかなか引かない方や今は特に何もアプローチをされていない方など、ご連絡をお待ちしております。
Q.半月板損傷を放置するとどうなりますか?
A.半月板損傷を放置すると症状の悪化や運動制限など日常生活に支障が出る可能性が高まります。
1. 症状が悪化する
・痛みの持続・増強
初期は動かしたときだけの痛みでも、徐々に常に痛むようになってしまいます。
腫れ(関節水腫):半月板のかけらや炎症で膝に水がたまりやすくなる。
ロッキング(膝が動かなくなる):損傷片が関節に引っかかり、膝が曲げ伸ばしできなくなる。
2. 半月板の損傷が進行する
放置して日常生活を続けることで、裂け目が大きくなり修復困難に。
縫合術で治せたはずが「切除しか選べない」状態に悪化することも。
3. 膝の関節軟骨が傷む
半月板はクッション機能を持つため、欠けると 骨と骨が直接ぶつかる ようになる。
関節軟骨がすり減りやすくなり、膝の摩耗が進行する。
4. 変形性膝関節症へ進行するリスク
半月板損傷を放置すると、10年〜20年後に 変形性膝関節症 へ移行しやすい。
特に「部分切除」や「放置」が長いほどリスクが高い。
将来的には人工膝関節置換術が必要になる可能性もある。
5. 日常生活への影響
・正座・階段の昇降が困難になる。
・膝が不安定で転倒リスクが増える。
・スポーツや趣味の活動に制限がかかる。
最初は痛みだけで留まることが多いですが、放置することにより症状が悪化、半月板の損傷過程が進行し、変形性膝関節症にも繋がるリスクが高まります。
是非早い段階で当院にお越し下さい。
Q.膝が「ポキッ」と鳴るのは半月板損傷と関係はありますか?
A.1. 膝の音の原因は様々です。
膝の関節音(クリック音)は必ずしも異常とは限りません。
主な要因としまして
・生理的な関節音(正常な音)
・関節内の気泡(窒素ガス)がはじける音。
・靭帯や腱が骨にこすれる音。
・痛みや腫れを伴わなければ心配いらないケースが多いです。
半月板損傷による音
・半月板の一部が関節内で引っかかり、「ポキッ」「ガクッ」と鳴る。
・ロッキング(急に膝が動かなくなる)を伴うことがある。
・音と同時に「痛み」「膝のひっかかり感」「不安定感」が出やすい。
変形性膝関節症による音
・軟骨がすり減り、関節面がゴリゴリこすれて鳴る。
・中高年に多く、膝のこわばりや慢性的な痛みを伴う。
2. 半月板損傷を疑うべきサイン
膝の音が以下の症状と一緒に出る場合は半月板損傷の可能性があります。
・膝が急に「ガクッ」と抜ける
・動かしたときに鋭い痛みがある
・膝が完全に伸びない/曲がらない
・繰り返し膝に水(関節液)がたまる
・膝が腫れる
3. 放置してよい音と注意が必要な音
放置してよいケース
・音だけで痛みや腫れがない
・運動後やストレッチ時に一時的に鳴る
受診した方がよいケース
・音と同時に痛みや腫れがある
・膝が動かなくなる(ロッキング)
・音が頻繁に出て日常生活に支障がある
膝が「ポキッ」と鳴る音は自然に出る音と膝の状態が悪くなって出る音に分かれます。
上記にも書いてあるように痛みや腫れを伴う場合は早急に施術をし、改善に向かわせることがとても大切です。
Q.半月板損傷と靭帯損傷は関係ありますか?
A.半月板損傷と靱帯損傷は関係しています。
【膝関節の構造と役割について】
1. 膝関節の構造と役割
・靭帯(前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靱帯、外側側副靭帯)→ 膝関節の「安定性」を保つ。
・半月板(内側・外側)→ 膝関節の「クッション」と「荷重分散」。
靭帯と半月板は 膝を守るパートナー のような存在です。
2. 同時損傷が起こることがあります
特に有名なのが 「不幸の三徴候」 と呼ばれる組み合わせです。
・前十字靭帯損傷
・内側側副靭帯損傷
・内側半月板損傷
サッカーやスキーなどで膝を強く捻った時に起こりやすいです。
3. 靭帯損傷があると半月板に負担がかかる
・前十字靭帯断裂 → 膝が前後に不安定 → 半月板がズレやすくなり損傷しやすい。
・内側側副靱帯損傷 → 膝の内側が緩む → 内側半月板にストレスが集中。
・後十字靭帯損傷 → 後方不安定性により外側半月板に負担が増す。
4. 半月板損傷が靭帯に影響する場合
半月板が裂けて関節の安定性が低下 → 靭帯へのストレス増加。
半月板切除後は靭帯損傷のリスクも相対的に高まるといわれています。
どちらか一方だけ、良くなっても一方が傷んでいれば再発や変形性関節症の進行につながるます。
日常生活で今は問題がないから大丈夫と思わずに症状が進行する前に当院に一度お越し下さい。
Q.半月板損傷に対しての予防はありますか?
A.予防方法はあります。予防することで将来の今後起こりえるリスクを減らすことが出来ます。
1.骨格矯正や姿勢矯正などでお身体のバランスやアライメントを整える
骨盤が歪むと膝にかかる負担も増えてきますので骨格矯正を行い膝、下半身への負担を減らします。
2. 筋力トレーニングで膝を守る
膝関節は筋肉のサポートがないと不安定になり、半月板に負担が集中します。特に以下の筋肉を鍛えることが予防につながります。
大腿四頭筋(太ももの前)→ 膝の伸展を支える。スクワットやレッグエクステンションが有効。
ハムストリングス(太ももの後ろ)→ 膝の安定性を高め、前十字靭帯への負担を減らす。ヒップリフトやレッグカールがおすすめ。
臀筋(お尻の筋肉)→ 股関節を安定させ、膝へのねじれストレスを減らす。サイドステップやヒップアブダクションが有効。
2. 柔軟性の確保
太もも前後・ふくらはぎのストレッチで膝の動きをスムーズに。
股関節や足首の柔軟性を高めることで、膝への負担を軽減し、歩行などもしやすくなります。
3. 運動時の注意点
ジャンプの着地フォーム→ 膝が内側に入らないようにする(ニーイン防止)。
方向転換の姿勢→ 膝だけでなく、股関節と足首を一緒に使って回転する。
サポーターやテーピング→ 膝の不安定感がある人や試合時に有効。
4. 体重管理
体重が増えると膝に直接的な荷重が増え、半月板への圧力も増大。
適正体重を維持することが長期的な膝の健康につながる。
5. 日常生活での工夫
長時間の正座やしゃがみ姿勢を避ける。
階段を降りるときは特に膝に負担がかかるため注意。
無理に重い荷物を持たない。
6. スポーツ別の予防
サッカー・バスケ:方向転換・急停止動作を正しいフォームで。
スキー・スノボ:膝を内側に入れすぎないよう意識。
マラソン:走行距離や路面の硬さに注意し、シューズを定期的に交換。
ご自身の状態に合わせて適切な予防をして行き、未来に起こるリスクを減らしましょう。
西巣鴨、庚申塚、北区西ケ原地域にお住まいの方はもちろん、その他の地域の方も大歓迎です!